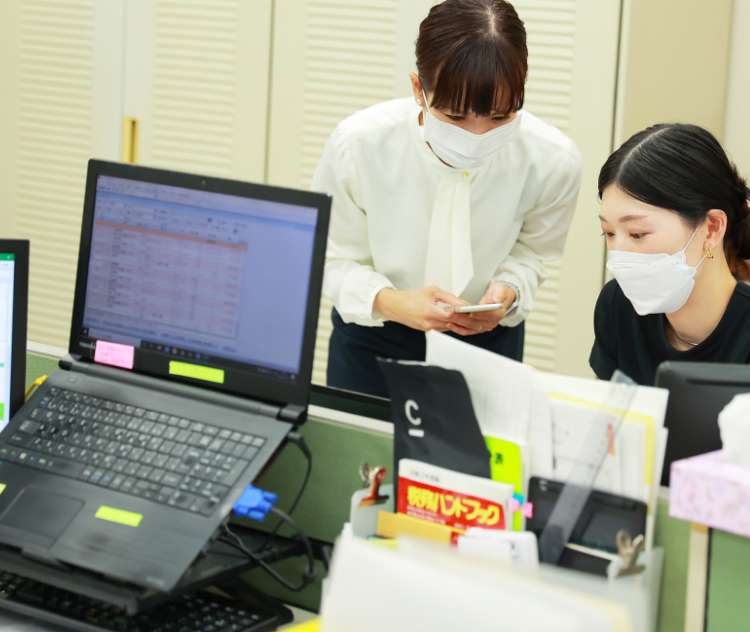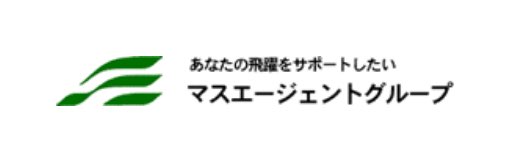2025年に施行される主な法改正について・ワンポイント解説
◆労働者死傷病報告等の電子化(1月~)
労働者死傷病報告は、労働者が労災で休業等した場合に、労働基準監督署に提出する書面です。
◆離職票のマイナポータル受け取り(1月20日~)
マイナンバーが被保険者番号と紐づいており、マイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行うこと等が条件となります。
◆高年齢雇用継続給付の見直し(4月1日~)
給付率の上限が15%から10%に縮小します。今後60歳以降の賃金水準の見直しや、定年延長への対応も必要に?
◆育児休業給付延長時の審査厳格化(4月1日~)
入所保留通知書等に加えて、保育所等利用申込書の写しや育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書の添付が必要となります。
◆出生後休業支援給付金の創設(4月1日~)
両親ともに14日以上の育児休業取得で、28日を上限に給付率13%を支給、育児休業給付金等と合わせて給付率合計80%となります。また、育休中は社保免除、雇用保険料なし、育児休業給付等は非課税のため、手取り100%相当の給付となります。
◆育児時短就業給付金の創設(4月1日~)
2歳に満たない子を養育するために時短勤務(育児時短就業)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに、賃金の10%を上限として支給されます。
◆仕事と育児・介護の両立支援(4月1日~、10月1日~)
子の看護休暇の目的拡充、小学校3年生修了まで延長など。
介護の申出があった場合に、両立支援制度の周知・意向確認を行うなど義務化。
10月からは、3歳~小学校就学前までの子を養育する従業員を対象に、柔軟な働き方を実現するための措置を選択して講ずる必要があります。
◆基本手当の給付制限の短縮(4月1日~)
教育訓練等の実施により自己都合退職者の給付制限を解除。
自己都合退職者の給付制限期間が、原則2か月から1か月に短縮されます。